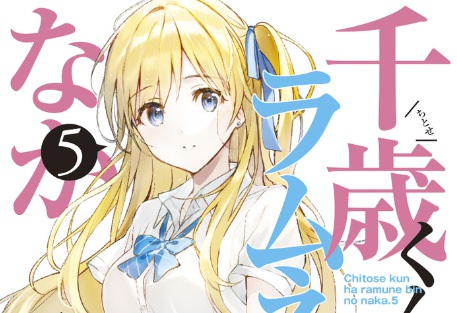どうもお疲れ様、大学時代は演劇サークルに入ってたカカオです。
大学生になるとサークルやバイトなど、様々なコミュニティに所属するチャンスが増えます。
でも知らない人だらけの場所に一歩を踏み出すのって勇気入りません?
僕ははっきり言って苦手です…。1人でいたほうが気楽ですよねぇ。
でも頑張ってコミュニティに足を踏み入れてみると、メリットが多くて入って良かったなって思えます。
というワケで今回は「大学生がコミュニティに所属すべき理由」について解説していきます。
※「サークル入ったりバイトも始めてみたいけど、知らない人の中に入るの恐いな…」と思っている方向けの記事です
大学生が何らかのコミュニティに所属すべき5つの理由

- 友達ができる
- 恋人ができる(かもしれない)
- 行動範囲が広がる
- 色々な考え方に触れられる
- 先輩の経験談を反面教師にできる
1つずつ解説していきます。
1、友達ができる
コミュニティにもよりますけど、友達ができる確率はめっちゃ高いです。
中には大学卒業後も連絡を取り合って会ったりする人とも出会える(僕はいます)
ぼっちを否定するワケではありません。一人の時間だって必要です。
でも友達がいることで得られる充実した時間や情報は、学生時代だからこそ味わえる魅力があります。
笑いあって遊んだり、テスト前には一緒に絶望したりなどなどw
あと友達がいることで会話が生まれます。
何言ってるんだと思われるでしょうけど、会話をしないと人と話すの苦手になりますよ。
大学卒業後、どんな仕事に就くにせよ人とのコミュニケーションは欠かせないからね。うん。
2、恋人ができる(かもしれない)
恋人については友達以上に運要素あるし、色々がんばらないといけません。
なので個人的にはあまり強く推すメリットでは無いんです。
ただどこにも所属せずに一人でいては、恋人ができる可能性はめっちゃ低いことは確か。
ちなみに僕の周囲には大学卒業後にサークル仲間同士で結婚した人もいるほどなので、大学時代のコミュニティは侮れません。
でも彼女作るの目当てでサークル入る出会い厨になっちゃダメ。
3、色々な考え方に触れられる

ほぼ間違いなく自分と全く同じ考え方の人なんていません。
- 自分とはちょっと違うか
- かなり違うか
- 真逆か
程度の差はあれこの3つのタイプがほとんどだと思っていいと思います。
そしてこれを苦痛に感じて疲れる人もいるはず。
でもコレって大学卒業後もついて回る問題で、十分に慣れておく必要があります。
コミュニティに入っておくと、そういった違う考え方に触れる機会に恵まれますよ。
もちろん辛いことだけでなく、共感や参考になる考え方をされる人との出会いだってあるかもしれません。
例えば、僕の大学時代にサークルで仲良くなった先輩が免許を取ったことがあったんです。
僕は正直言って免許なんて面倒で取る気無かったんですけど、先輩の車の話とか聞いてるうちに影響されて自分も免許を取り、中古で車まで買いました。
一人旅もたくさんしてめっちゃ楽しかったですね。
もし僕がサークルに入らずにいたら、免許も車も持ってなかったでしょう。とてもプラスになりました。
後述しますけど、あまりにも合わない人ばかりで嫌なら、そのコミュニティを抜け出しちゃっていい。 僕も嫌な場所からは撤退してる。
行動範囲が広がる
「一人でもいろんな所に行ってれば行動範囲広がるでしょ」
って思われそうなんですけど、意外とそうでもありません。
例えば入学したばかりの頃、先輩が色々なところに連れ出してくれて僕はとても助かりました。
よく行くカフェや美味いラーメン屋まで、とにかく新しい情報がたくさん入ってきたのを覚えています。
あと友達と一緒じゃないと行かない場所にも行けますね(一人だとカラオケや映画館に行かない人もいるのでは?)
前述で僕は一人旅をするようになりましたけど、それだって元を辿れば先輩に影響されて免許を取ったからです。
一人では限界があります。
先輩の経験談を反面教師にできる
これは個人的にめっちゃ推したいメリットです。
コミュニティに所属していると、概ね先輩たちが存在します。
そんな彼らの経験談、もっと言うなら失敗談に耳を傾けて、反面教師にするのです。
失敗談ってとても貴重で、自分は失敗することなく失敗を追体験できるんです。
失敗談を聞いたら
- 自分ならどう対処するか
- どう回避するか
この辺りを考えるとためになりますよ。
大学生ならサークルの先輩にテストやレポート、就活について色々聞いてみるといいですね。
【悲報】コミュニティはピンキリです

ここまでコミュニティに所属するメリットを伝えてきましたけど、悲しいことに微妙なコミュニティも存在します。
例えば僕は大学時代の一時期に写真サークルに入ってたんです(一眼レフを買うほど写真が好きだったので)
ところが僕の大学の写真サークルは部室でダベって麻雀したりゲームしてばかり。
いる人たちも僕とは気が合わない感じ。考え方の違いという意味ではコミュニティのメリットを享受できる感ありますけどね。
ただ純粋に「ここにいたら自分がダメになりそう…」というのは察しましたね。
逆に自分にピッタリなコミュニティもあります。僕の場合は演劇サークルがそれでした。
演劇にはあまり興味はなかったんですけど、サークルの人たちと気が合った結果、演劇にも興味が持てました。
こんな具合に、コミュニティと言ってもピンキリなので注意してください。
自分に合わないコミュニティに入った場合の対処法
「コミュニティからの離脱ってどうやるの?」
って思われそうなので書いておきます。
サークルの場合
大学のサークルなど趣味のコミュニティならフェードアウト。行かないようにすればそれでオーケー。
自然にいない者として認知され、その認知すら忘れ去られますw
ちなみに僕はフェードアウトしたこともありますし、された側にもなりました。全く問題ありませんでしたね。
バイト先の場合
バイトの場合は責任者(店長とか)に退職することをハッキリと伝えてください。
よくバイト仲間に相談する人もいますけど、それで辞められるワケじゃないし意味ありません。
関連記事:バイトを1日で辞めるって有り?無し?【経験談有り】
大学生が所属するコミュニティならこの3つ
大学生が所属できるコミュニティでオススメなのは以下の3つです。
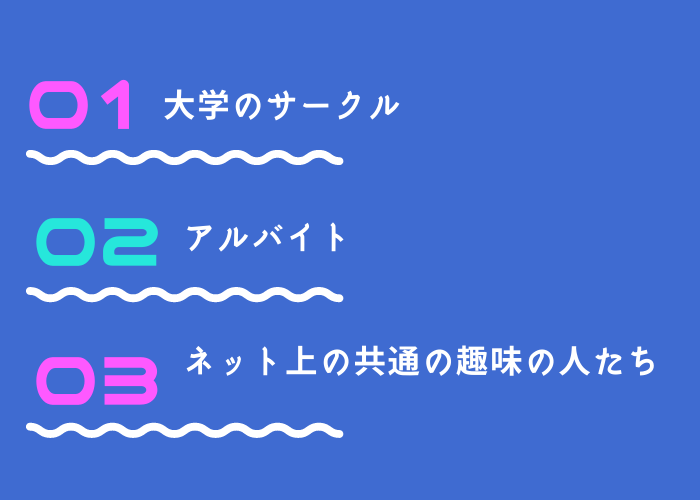
1つずつ解説していきます。
大学のサークル
大学生にとって1番身近で手軽なのは、やはり大学内にあるサークルです。
友達ができれば頻繁に会えますし、講義やレポートの情報を共有できるのもポイント高い。
前述のとおり先輩たちからは失敗談とか聞けるかもしれないし、有益なことも多いです。
運動系から文化系まで色々あると思うので、自分に合いそうなところに顔を出してみましょう。
アルバイト
自分とは全然違う世代や考え方と出会いやすいのはアルバイトです。
今でも覚えてるんですけど、大学時代のバイト先でバンド活動しながらフリーターをやってる25歳の人がいたんですよ。
その人、大学卒業後からその生活を始めたそうです。
「大学を卒業したら就職する」っていうのが当たり前だと思っていたんで、考え方の違いに驚きましたね。
合わせて読みたい記事:【落ちても問題なし】大学生がバイトの面接に落ちまくりな5つの理由
ネット上の共通の趣味の人たち
Twitterを眺めていると、趣味で繋がってオフ会を開いている人たちって結構多いんですよね。
僕はWEB小説とプラモが好きなんですけど、どちらの趣味でもオフ会を開いたりして楽しそうにしてる模様。
年齢の幅も学生から社会人まで幅広い感じで、しかも趣味で緩く繋がってるからバイト先のように辛くなるなんてことはなさそう。
以上のことから、緩くコミュニティに関わりたい方におすすめ。
もちろん、いきなり「会いませんか?」などと接触はしないように。それはただの出会い厨だから。
大学生コミュニティに所属すべき5つの理由|まとめ
大学生がコミュニティに所属したほうがいい5つの理由を書いてきましたが、要するに
『コミュニティに所属すると見識が広がるよ!』
ってことです。
見識の広さは社会人になってからも活きてきますので損することはありません。
とはいえ前述の通り合わないコミュニティも存在します。
自分には合わないと思ったら離脱も考えましょう。これもまた、社会人になってからも役にたちますから。
▼合わせて読みたい記事